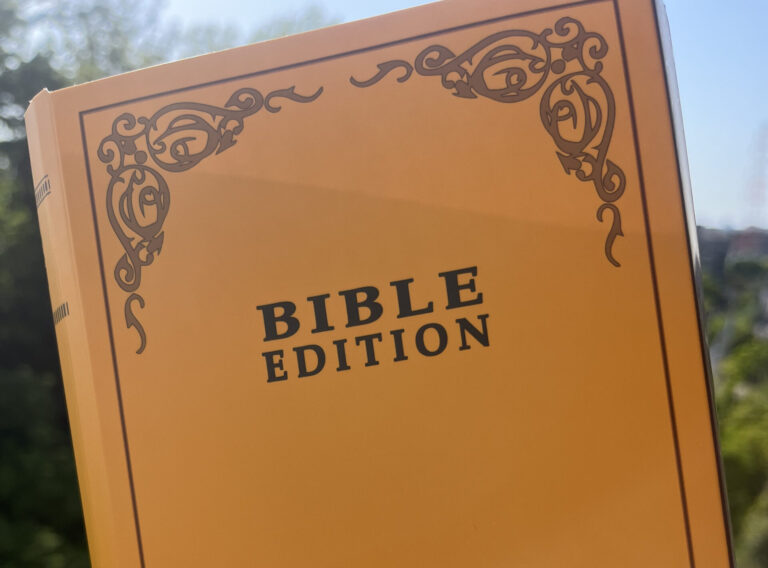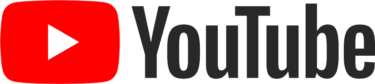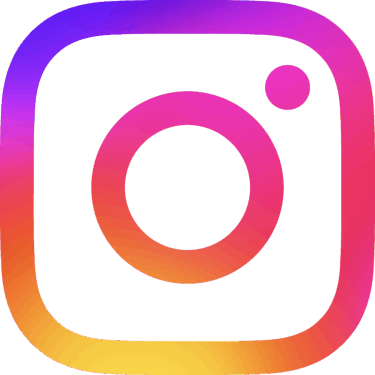この言葉の持つ威力と無責任さについて言及したい。
※私の文体が怒ってるように捉えられるかもしれないけれど、怒ってはいない。笑
私はこの2年間、自分の信仰を含めて「信仰とは何か」を探してきた。
この疑問から派生し、本論の結論から書きたい。
「聖書に書いてあるから」という表現や、聖書の言葉を添えて自分の意見を伝えることで相手に真理を伝えようとする行為は多くの場合、当人のエゴであると私は思っている。
なぜなら、
真理とは状況や相手によって変わらないものであると定義されているけれど、真理を伝えることが愛であると伝える側が主張する場合、愛より正義が強くなり、乱暴になり得る。
この言葉を言われつつ、シンプルに思いやりを感じなかったことを多く経験した。(そして私も無意識にそれをおかしたと思う。私は多くの人と聖書を読み交わしてきたり、リードさせていただく機会があったので、自分がおかしたかもしれない可能性に気づいた時、一人一人に本当に謝った。)
私は聖書の言葉は「普遍的で偽りなき神の言葉であり、真理と愛が書かれている」と信じている。
だから、「聖書にはこう書いてある」と言われると反論することを躊躇う。
聖書解釈はいつの時代も非常に難しい。
神学体系も含めて、字義的理解をするか否か、66巻の書物ごとに解釈が変わる。(旧約聖書と、キリストが現れる新約聖書を合わせて66巻が合体して1冊の聖書と呼ばれている。)
例えば、詩的解釈は旧約聖書のどの文化や出来事を背景にしているのか
文学的解釈をすべきなのか、予言的解釈をすべきなのかなど、読み方がわからないと本来の筆者の目的と違った理解をすることは往々にある。一部だけ切り取ることは本来できない書物であると思っている。
(よくあるのは、Ⅱコリントという書物に「不信者とつり合わないくびきを一緒につけてはいけない」とある。このみことばを用いてクリスチャンとクリスチャンではない人は結婚すべきではないという解釈がある。私はこの意見に賛成していた。けれども、本来のこの文脈は「教会全体に向けて話されていること」であって、個人間における結婚に言及しているわけではない。もちろん信者と未信者が一緒に生活したら面倒が増えると思うが、この箇所を聖書解釈にぶち込むのは些か物議を醸すようである。そもそも誰が福音をどのタイミングで信じるかなんて誰にもわからない。わからないからこそ、わざわざ冒険をする必要はないと教えられてきた。でもそれは非常に人間的で狭く、選民的な考え方でもあるように思う。)
以下のような言葉を聞き、
もう私の中では違和感や嫌悪感が拭えないようになっていることに気づいた。
「彼はクリスチャンなのに、自分のやりたいことがないなんてもったいない」
「聖書にはクリスチャン同士で結婚すべきとはっきりと書いてある。信仰者がそうでない相手と結婚するのは神様よりその異性を優先した結果だ」
「神様は男性は男性として女性は女性として最善を持ってあなたを美しく生かしていると書かれている。同性愛者として誰かと愛を深めることを神は望んでいない」
「信仰のある人は、既に信仰のある異性の中から結婚相手を選ぶべき」
私自身、友人に言われた言葉で、今思うと「は?」と思った言葉がある。
「あなたがクリスチャンじゃない人と付き合うと決めたら反対する」
「神様の啓示や御言葉の方が、あなた個人が感じることより大事」
私は素直な方なので言われた時は「そうなんだ…」と思ったこともあった。(特に後者)
でも今、冷静に思う。
あんた、どんだけ偉いの?
あんた、神なの??
全部偏見じゃない?宗教的だな。
と。
本人は正義を持って愛を伝えた気になっていると思う。
聖書の真理を伝えること自体が愛の行為であると思っている人は多いからだ。けれど、言われた私は一ミリも愛を感じなかったし、この人は「さとみ」ではなく、「クリスチャン」というラベルのついたさとみと付き合っているのだと思った。
しかも言った当人は言ったことさえ忘れているということが判明し、その無責任さに呆れた。
信仰者ならこうする/こうすべき。
信仰者ならこれはしない/してはいけない。
そうやって私たちは方程式を求めてしまう。
そういう安直な行動を私たちは容易に考えてしまうのだと思う。
宗教観に関わらず、どんな人生でも私たちは方程式を求めている。
安心するし簡単だからだ。
そこから解放させるのが福音であるにも関わらず、
これに気づかないとまた福音はこうだからと言って、
自分の世界を狭め、人にもそれを強要するサイクルになる。
「真理はあなた方を自由にする」はずなのに、なんでこんなに苦しかったのか。
その理由の一つはいつも広い世界を感じたい、
常に目に見えるそして目には見えない新しい景色を見たいと願っている私にとって、
狭くて苦しい、とりかごの中にいるような気分だった、と表現できる。
もちろん、素晴らしい人々に出会って本当にさまざまな喜びや
益となることを経験させていただいた。
その上で神様は、もっと広くて愛があって、
もっと大胆に様々なことを与えたいし一緒に経験したいと常に願っている。
その領域は私たちの想像をはるかに超える。
それは、聖書の御言葉の行間にこそ、神がいることを思わせる。
私たちは文字に表されていない神をもっと楽しみ、喜び、
余白に隠れた神と文字に書かれた神とを織り合わせ、
何度も新鮮に出会い関係を深めながら探求するのが人生の面白さであるのだと思う。
(こういうことを言うと、自由主義神学(=リベラル)だと思われそう。
けれど、そうやって、保守派とか福音派とか聖霊派とかカルバン主義とか、
そもそも小さな母数なのに勝手にいちいちカテゴリーに分けられるのも好きじゃない。)
こう実感を伴って思うのは私が無意識に方程式を求め、
「こうしたら神様は喜ぶ」とか「こうしたらいい信徒だ」と思い込んで、
自分に課していたからだと回顧している。
自分でとりかごを作り、
鍵の開いてるとりかごから出られなくしていたのは
他でもなく、わたし自身だった。
ある友人の11歳の娘さんが、「自分には信仰がないからもう教会に行かない」
と涙を流して言ったらしい。
なぜ彼女は泣いたのか。
理由は、自分は信じていないということと教会に行かないということを言ったら、
娘として一緒に住めなくなるのではないかと怖かったからだったという。
その時、母である友人は大きく悔い改めて、(悔い改めるとは、神に向き直るという意味)
イエスの愛に生きることは「〜すべき」「〜したらいい/悪い」
「聖書にはこう書いてある」から解放されることであると改めて実感したという。
救いに至る門が狭いと書かれているのは
多くの信仰者がキリストのように
愛だけに生きることの本当の意味をわかっていないからだと痛感した、と。
またある50代の友人の夫は昔ポルノ依存症で、
妻である友人は長年苦しんだことを打ち明けてくれた。
しかし彼女が言ったのは「聖書にはこう書いてあるのにと夫を責めたし、
自分に女性としての魅力がないと思って深く悲しんだ。
けれど、そこに私の罪があった。彼自身に問題の本質があり、
彼との関係が問題だと思っていたけれどそうじゃなかった。
「聖書はこう言ってるから」という正義に縛られて物事を解釈し人に教え、
裁く自分自身に、自分が一番苦しんでいたことに気づいた。
そこから解放されるために、この問題が私のために起きたのだ」と。
謙遜で寛大な分かち合いをしてくださった信仰の先輩に出会えたことを心から感謝している。
そして、ここにこそ福音の力がある。
「あの人に問題がある」「まだ変わらない」そう思う渦中にいる時、
私たちは自分と神との関係の中にどんなレッスンがあるのかを
見出すことを難しくしているかもしれない。
なぜなら、福音は「私」を生かす神との関係性の中に輝くものだからだ。
他の人は介在し得ない。
そして思うのは、「聖書に書いてある」ことが出来ないから、
そのためにキリストは十字架にかかって死んだわけで、
そこに自分や人を勝手に縛り付けるのはやめよう、
偉そうに教えてくれるな、と。
これからは益々、
私と神との関係を大切にしていきたい。
その神とは私の直感に働きかけ、感情を知っておられる。
自分の正当性を誇示する小さな存在ではない。
そして信仰とは、
神の恵みが先にあり、
その応答として掴んで握った手をたとえあなたが離しても、
絶対にあなたを離さない神の愛の元にいるという
信頼関係であると結論づけて終わりたい。
それは、私たちが「聖書にこう書いてある」だなんて言ってられない、
理解出来ない程の愛によって、
持続可能なものとして今も絶えず脈打ち、私たちを生かす力である。